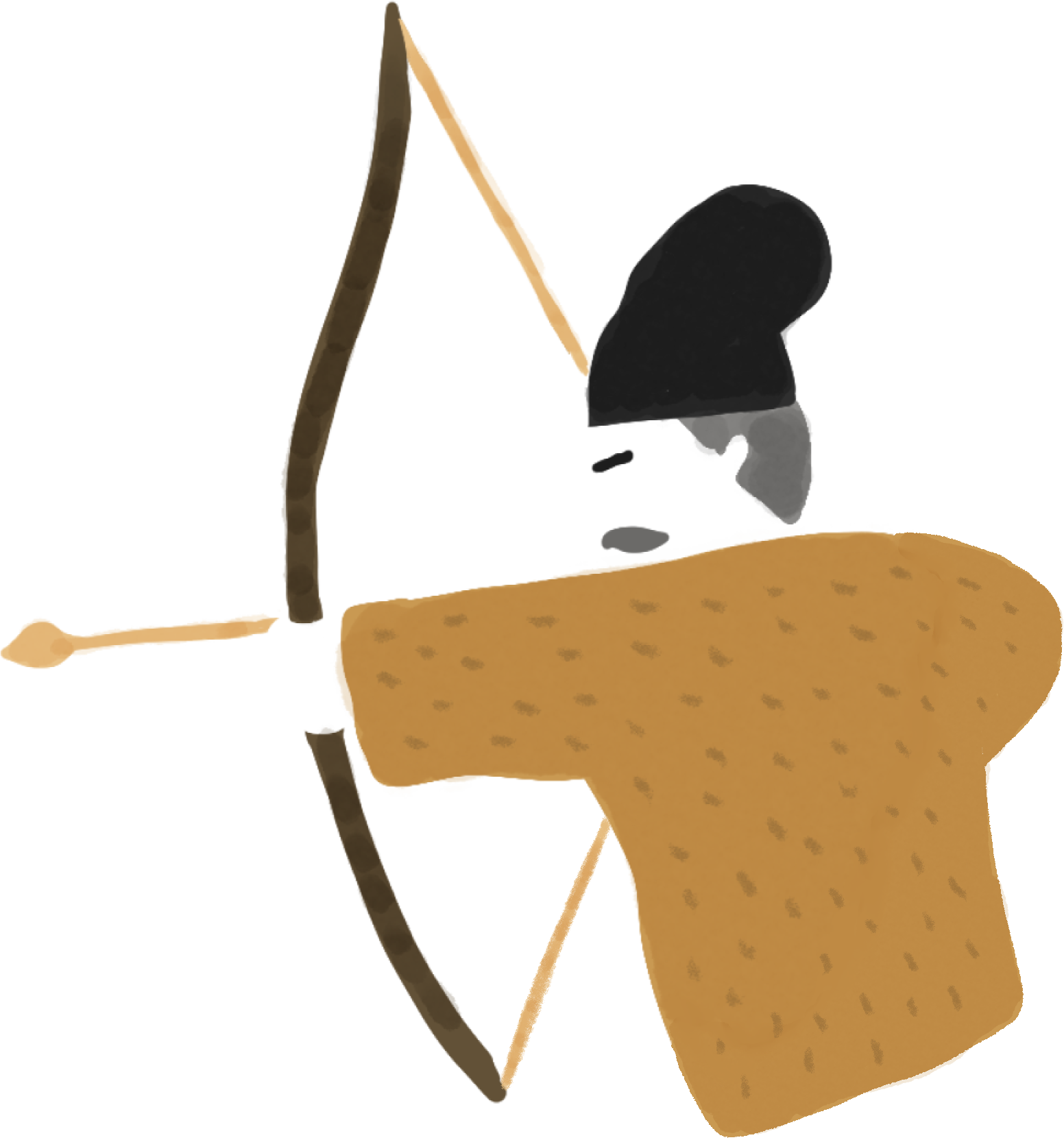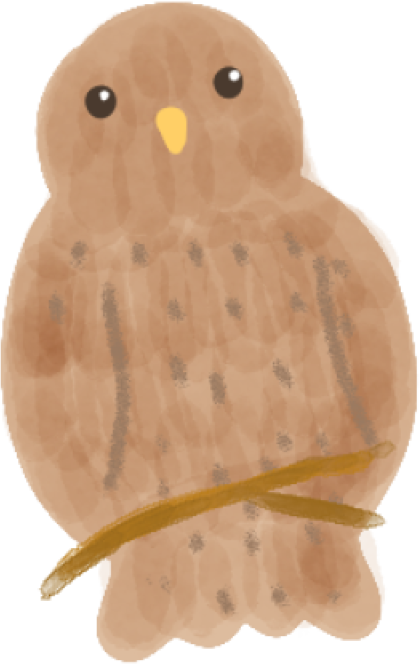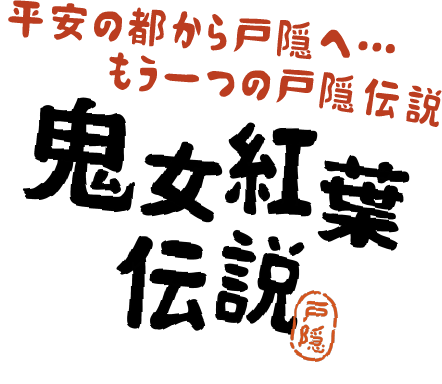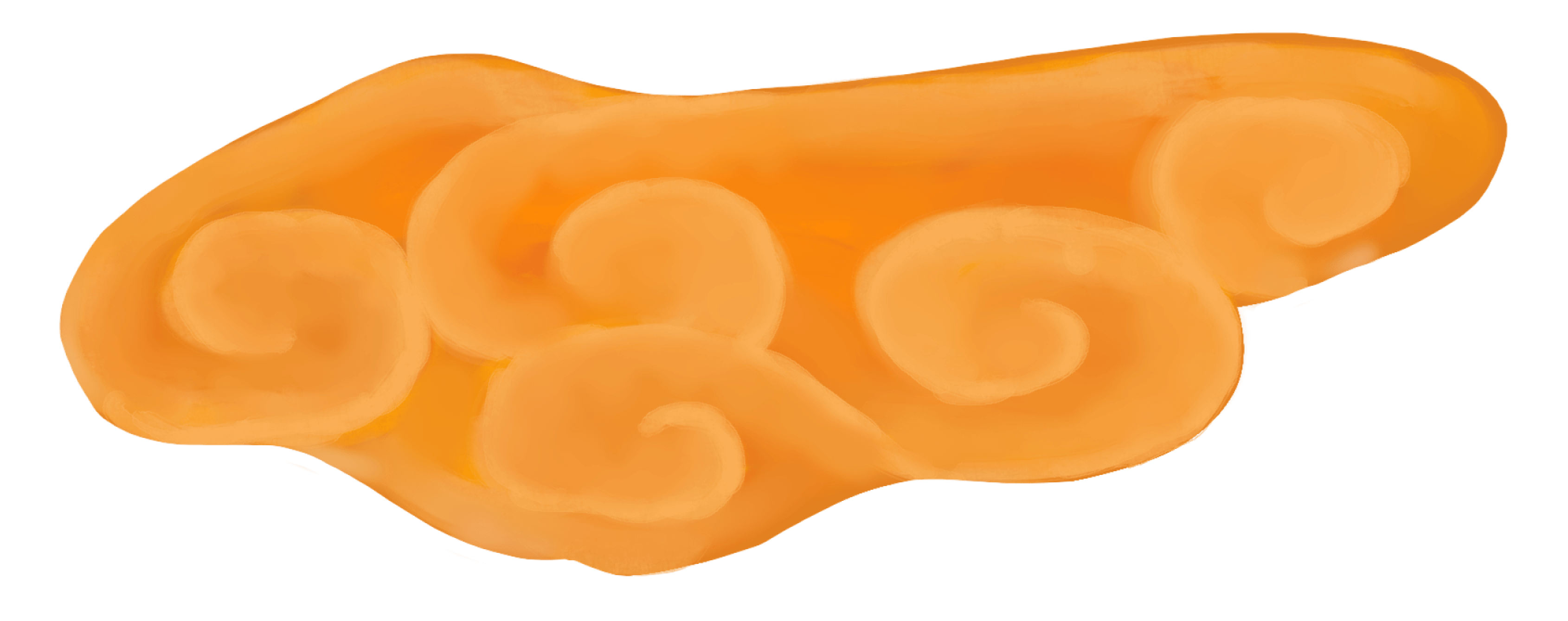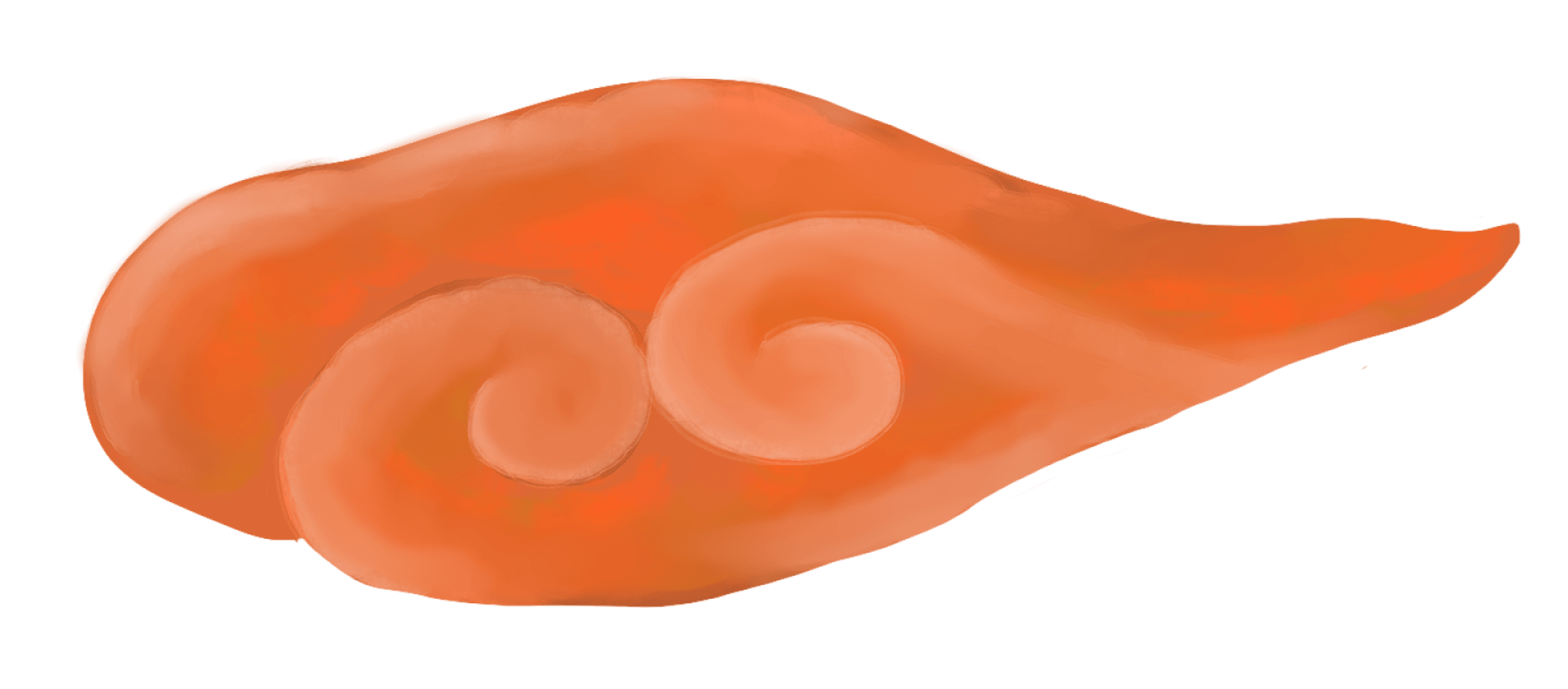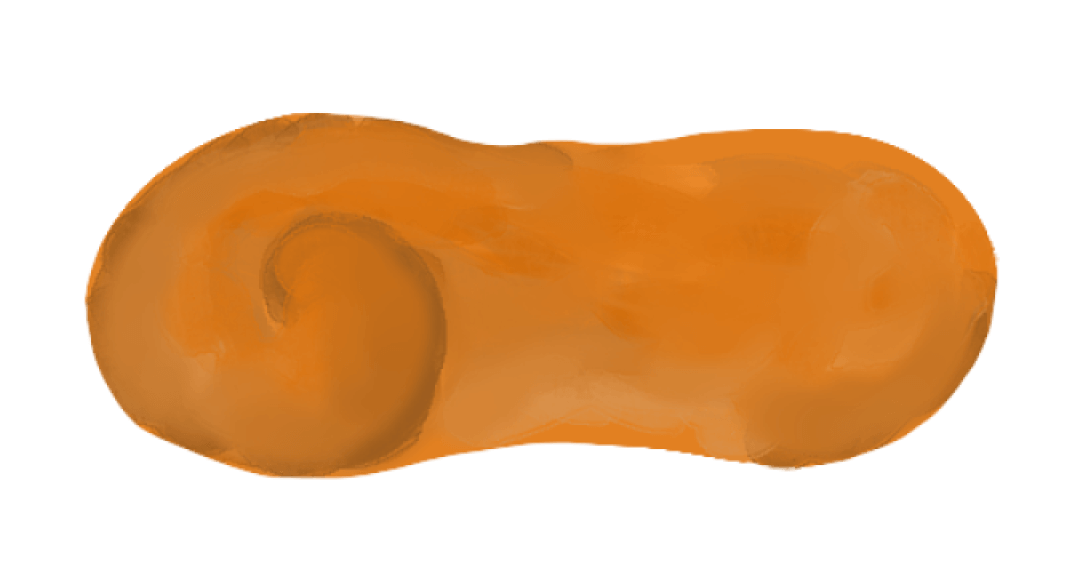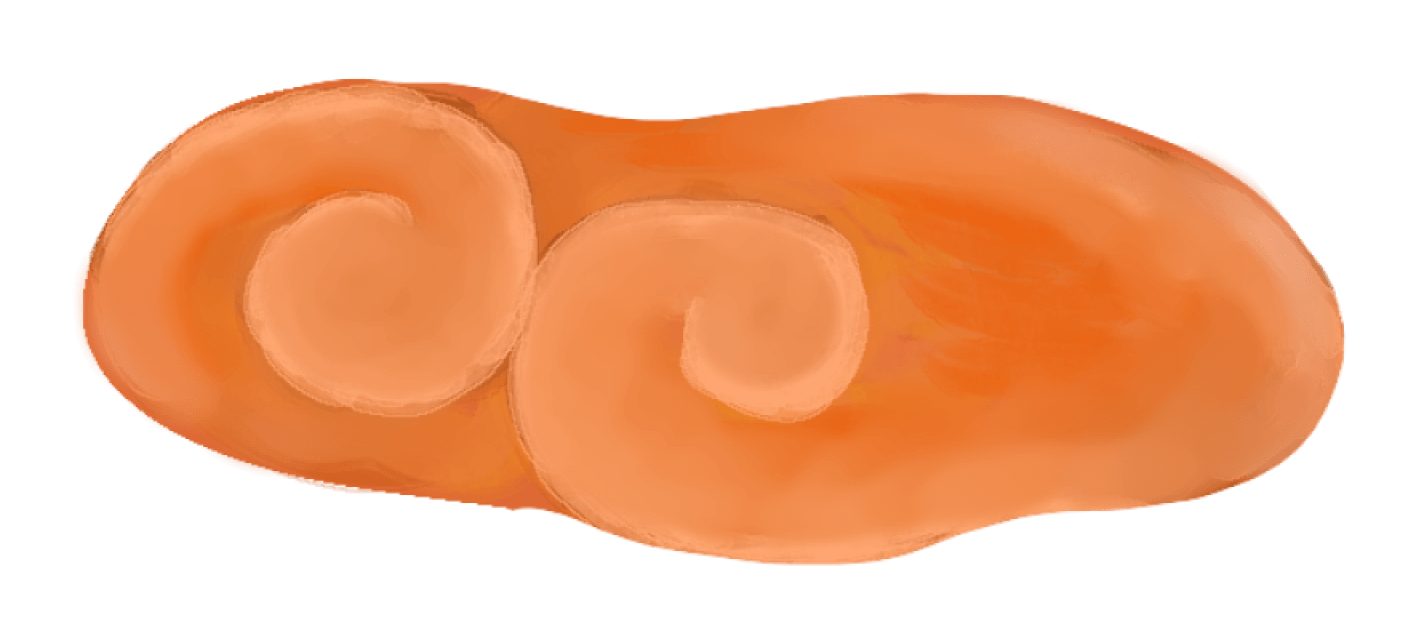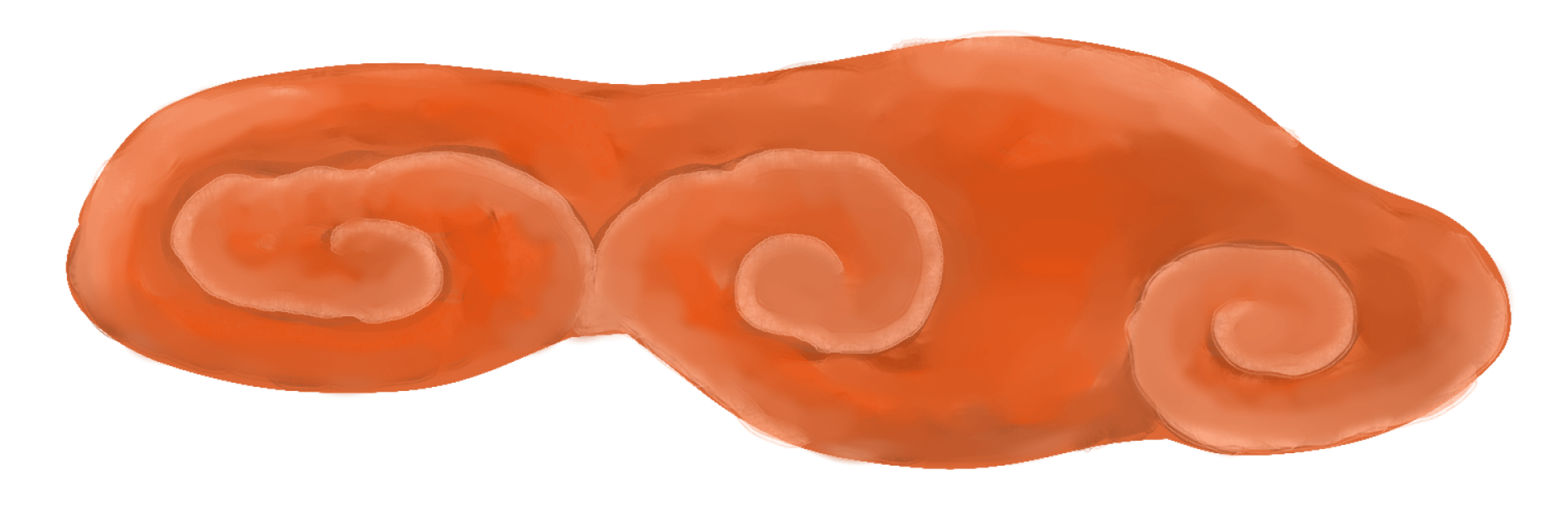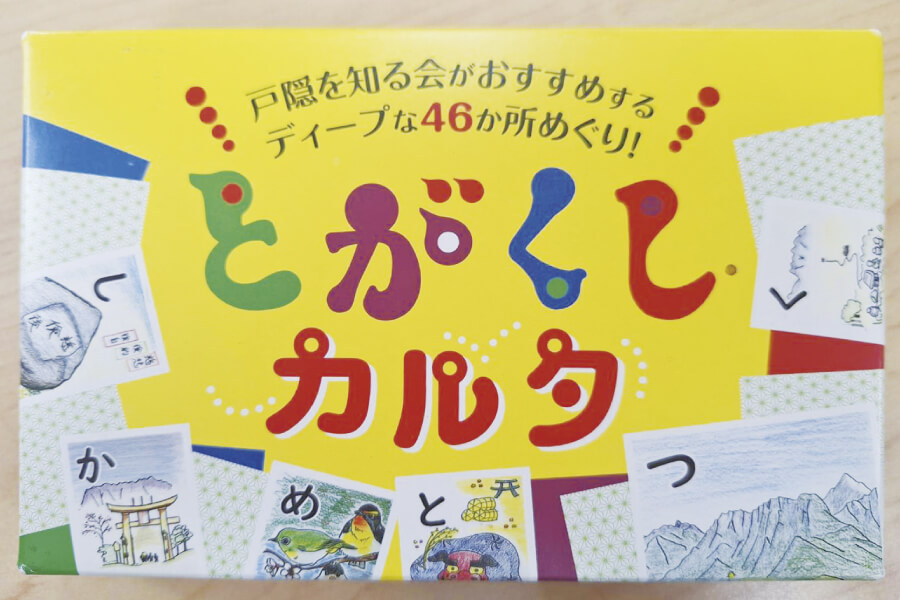むかしむかし、京の都を追われた一家の末裔に笹丸という男がおりました。子宝に恵まれなかった笹丸と妻の菊世は第六天魔王に願い、ひとりの女の子を授かります。その子は呉葉(くれは)と名づけられました。
都での再起を夢見た笹丸は、菊世と呉葉を連れて上洛。呉葉は紅葉(もみじ)と名を改め、その類まれな美しさで源経基の側室となりました。しかし、正室を呪った疑いをかけられ、戸隠(とがくし)・鬼無里(きなさ)へと流されてしまったのです。
はじめこそ村人たちと仲むつまじく暮らした紅葉ですが、次第に都への思いを募らせ鬼女へと変貌します。悪評を聞きつけた朝廷は平維茂(たいらのこれもち)に討伐を命じました。戸隠で激しい戦いを繰り広げたすえ、とうとう紅葉は退治されました。戸隠の里では、恐ろしい鬼女の物語として、そう語り継がれています。
一方、鬼無里では村人たちに教養を授けた気高い貴女として親しまれている紅葉。謎多き伝説の真相は、いまも山の奥深くに眠るとか。果たして紅葉の正体とは…
答えは、伝説の舞台を訪ねてこそ見えてくるのかもしれません。


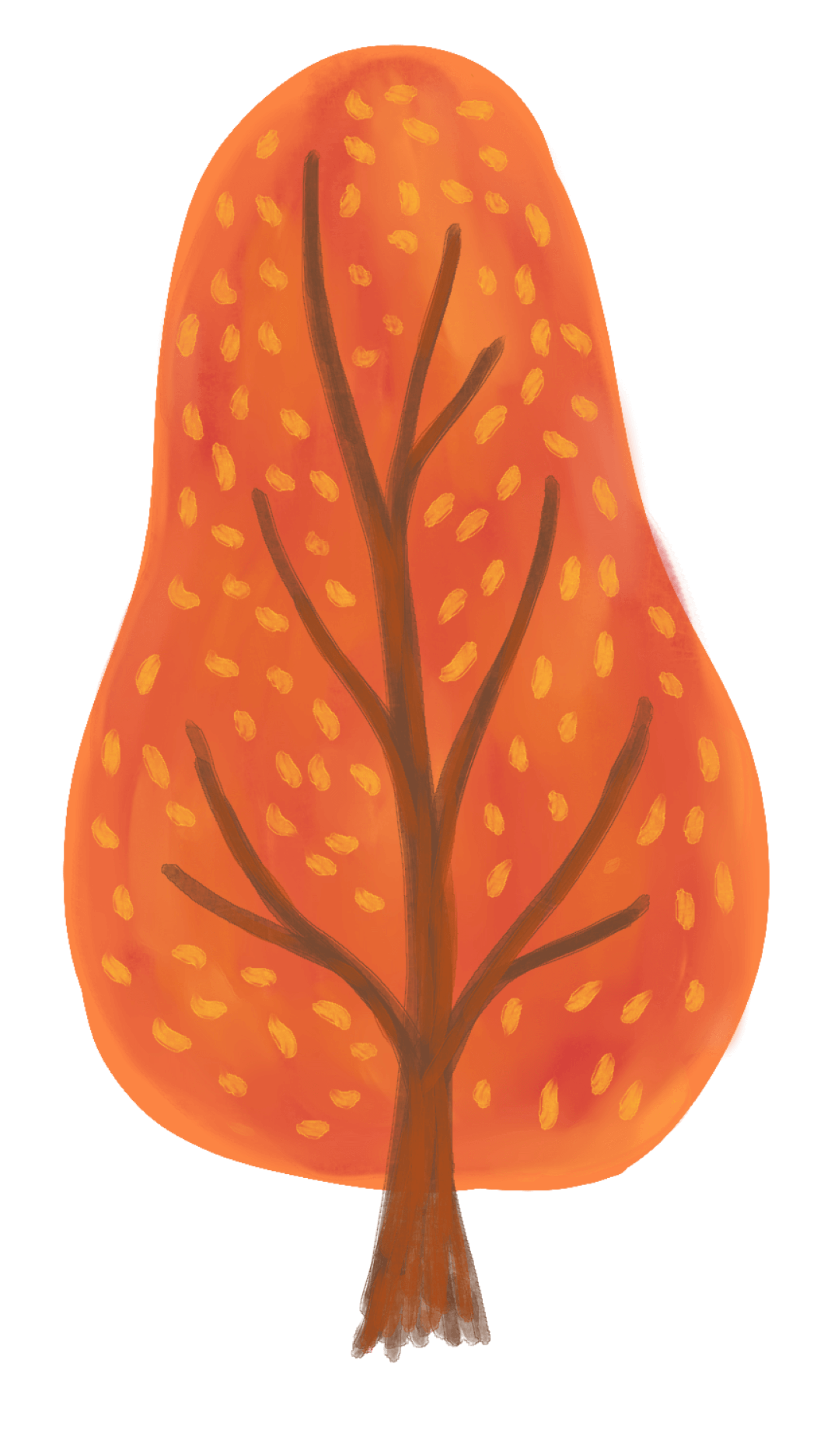
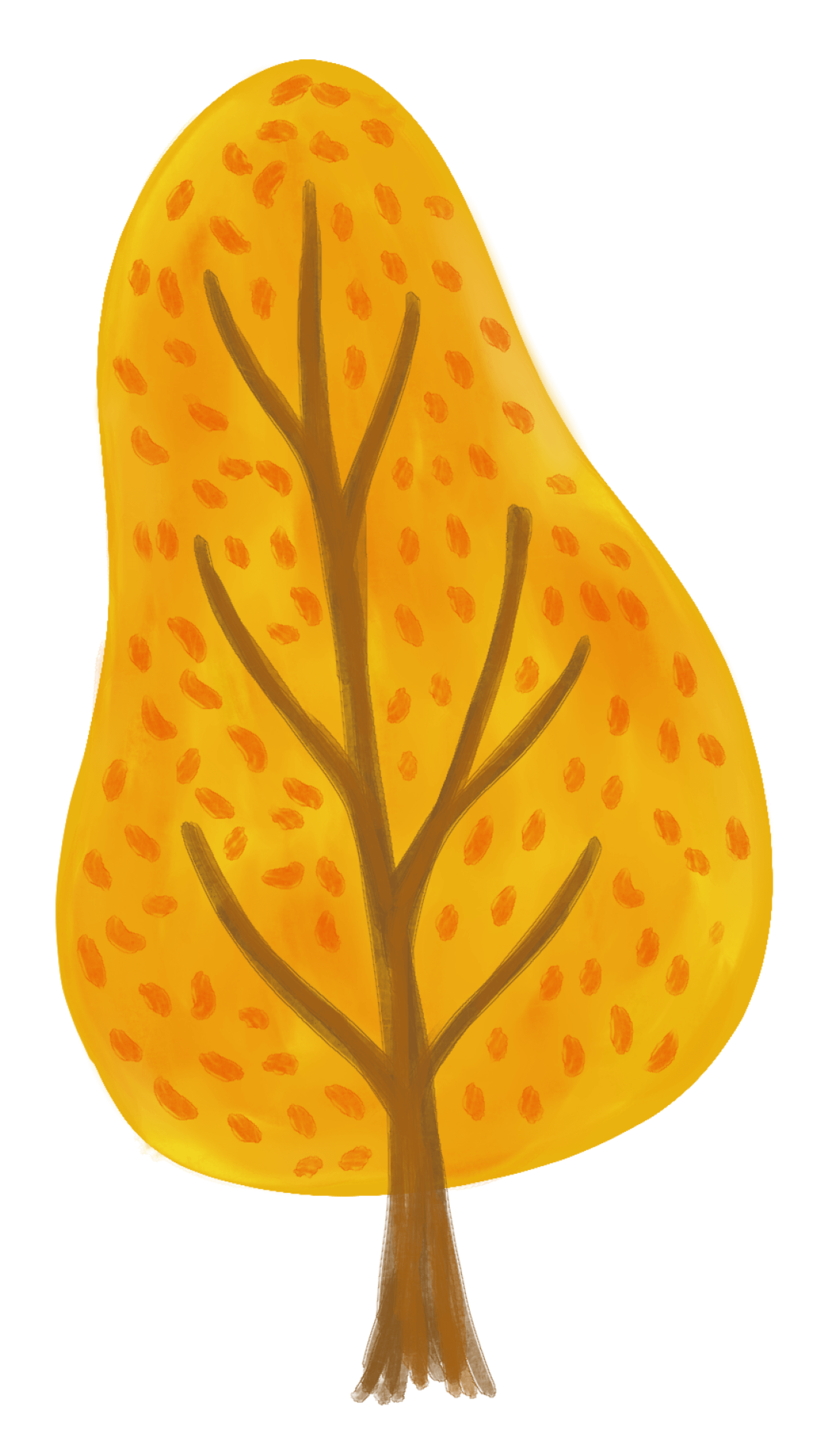

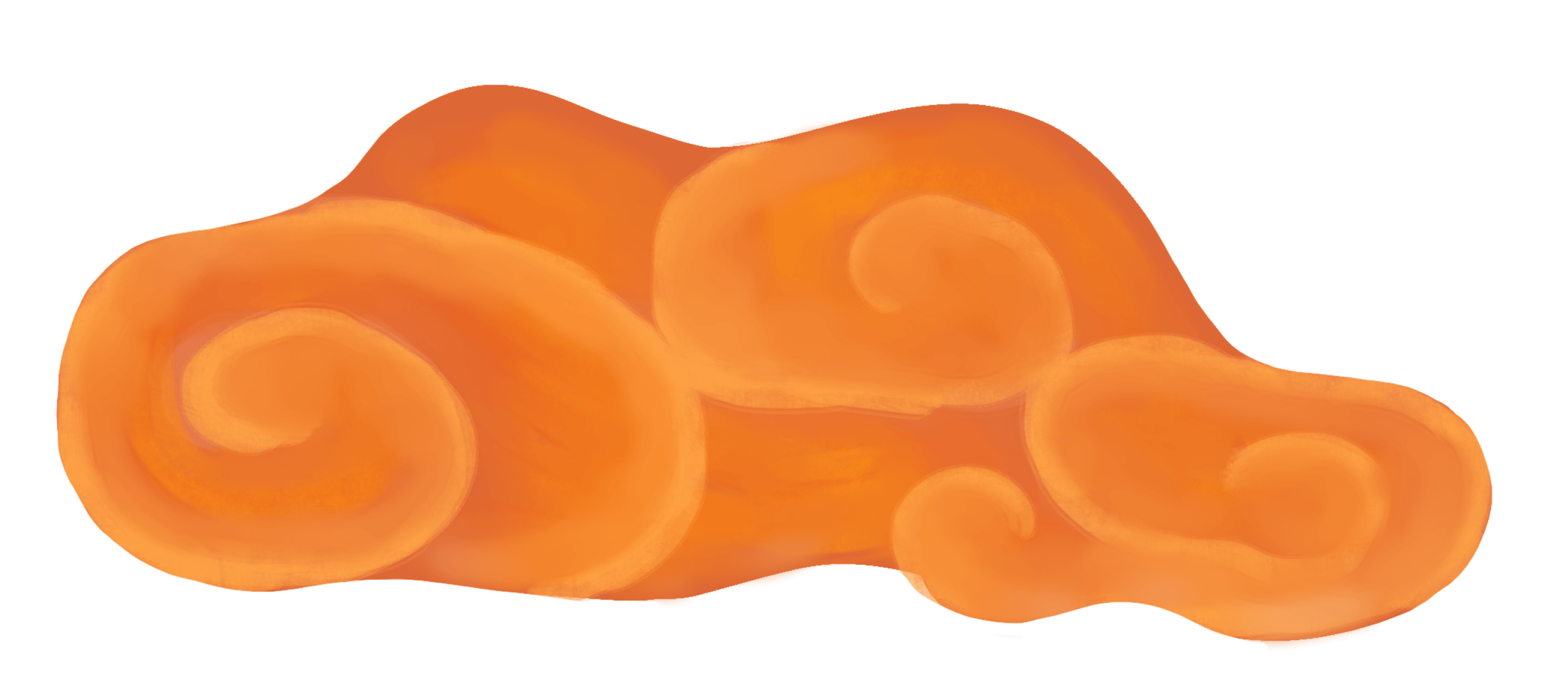
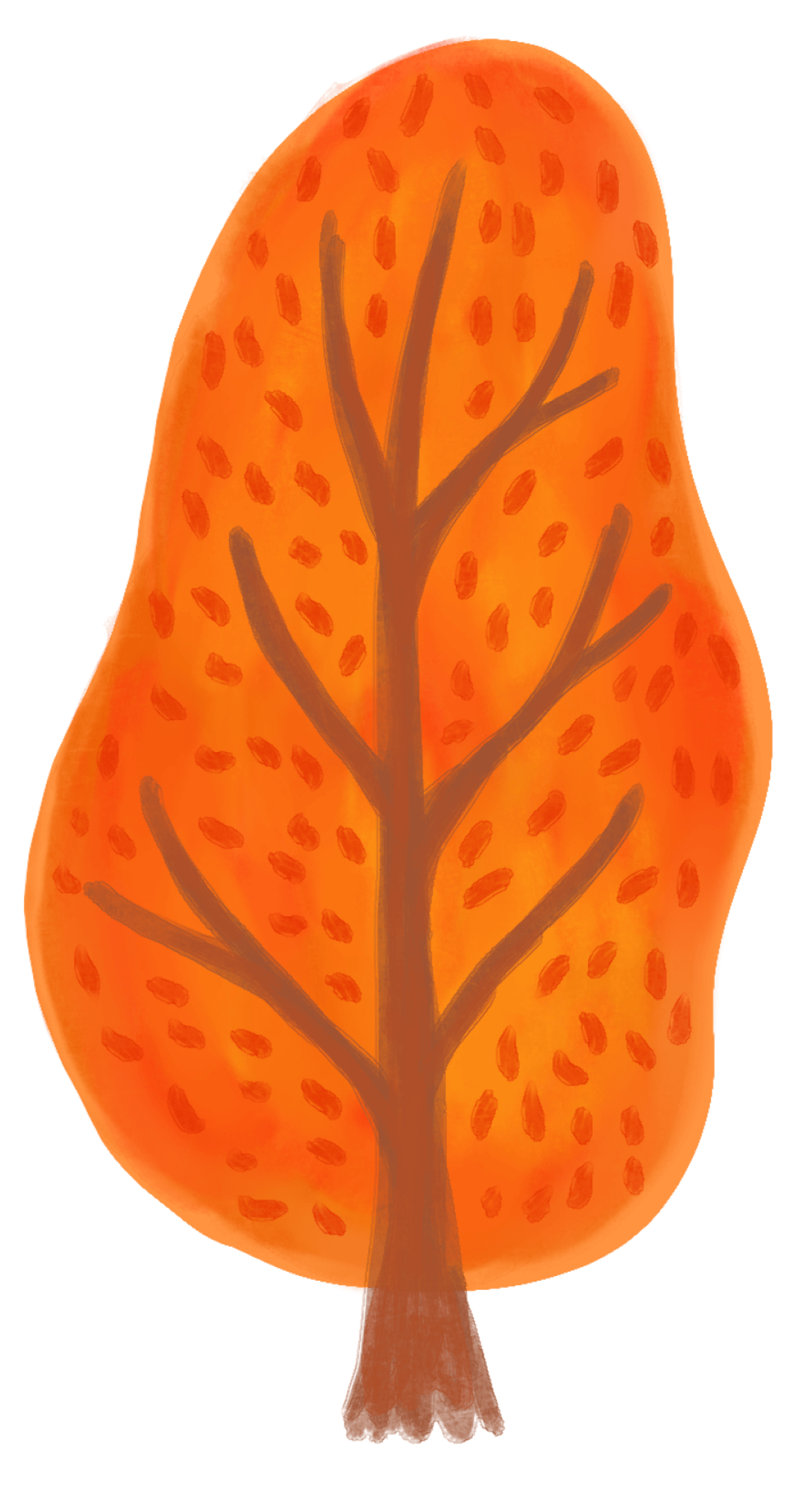

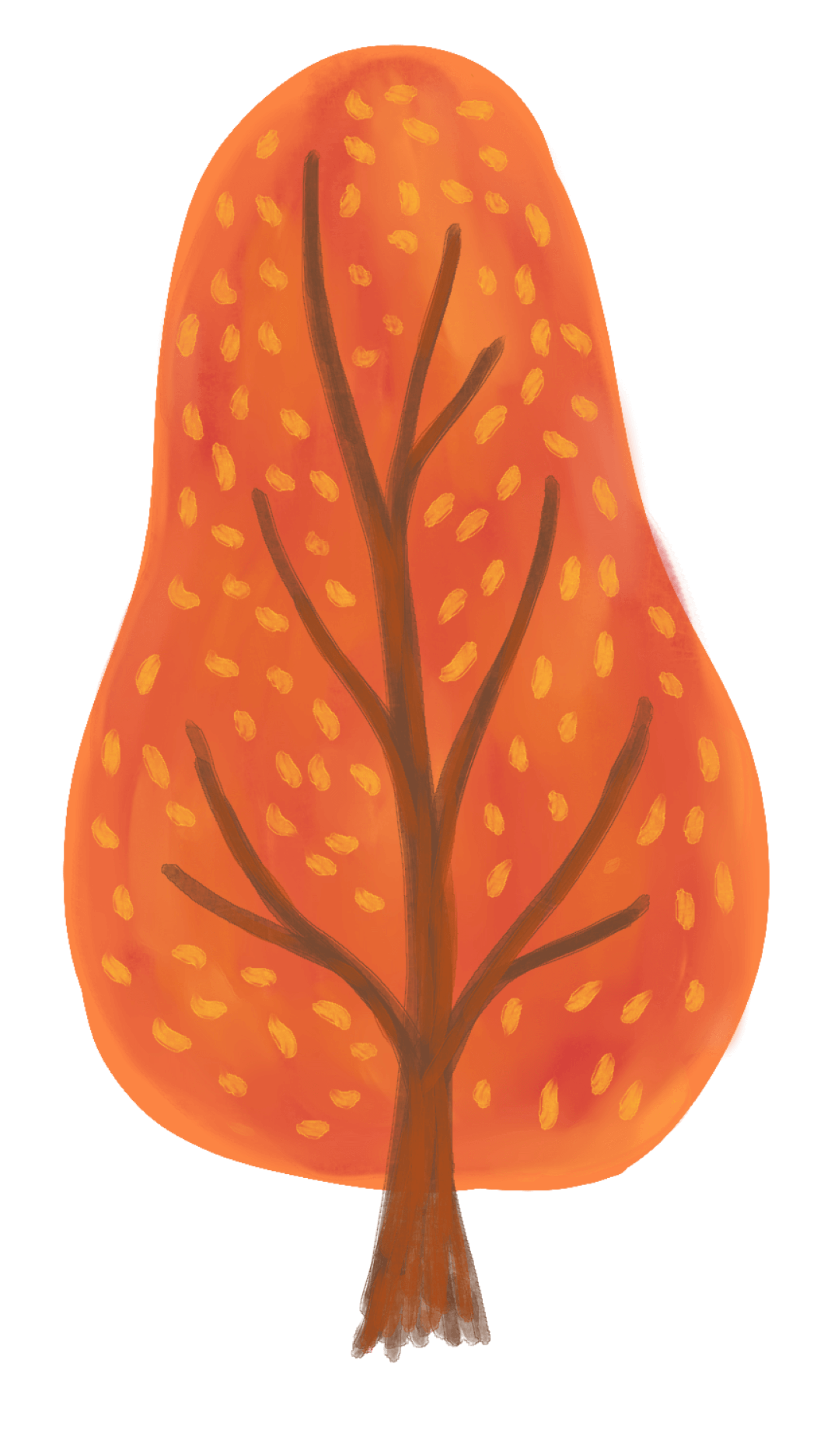

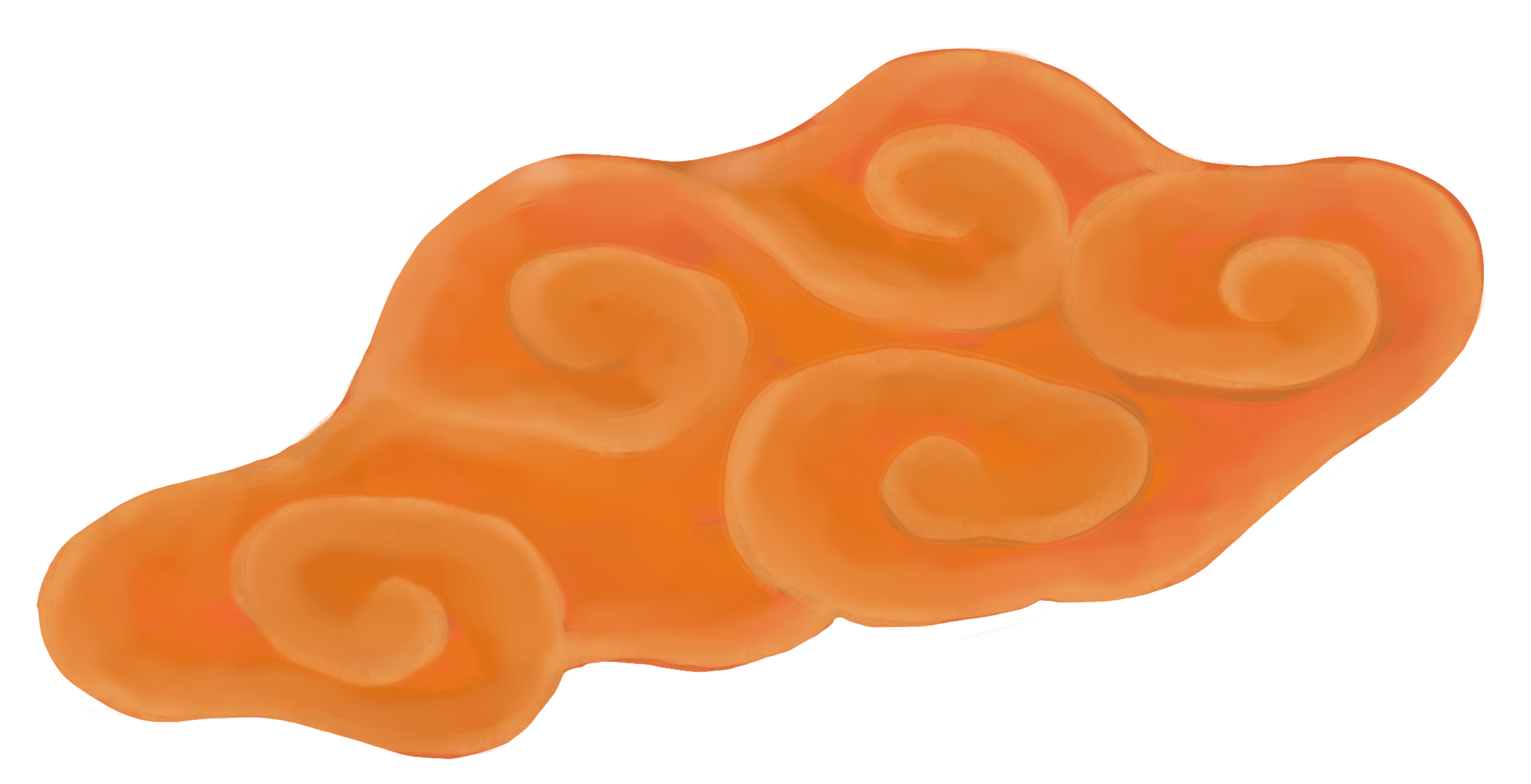
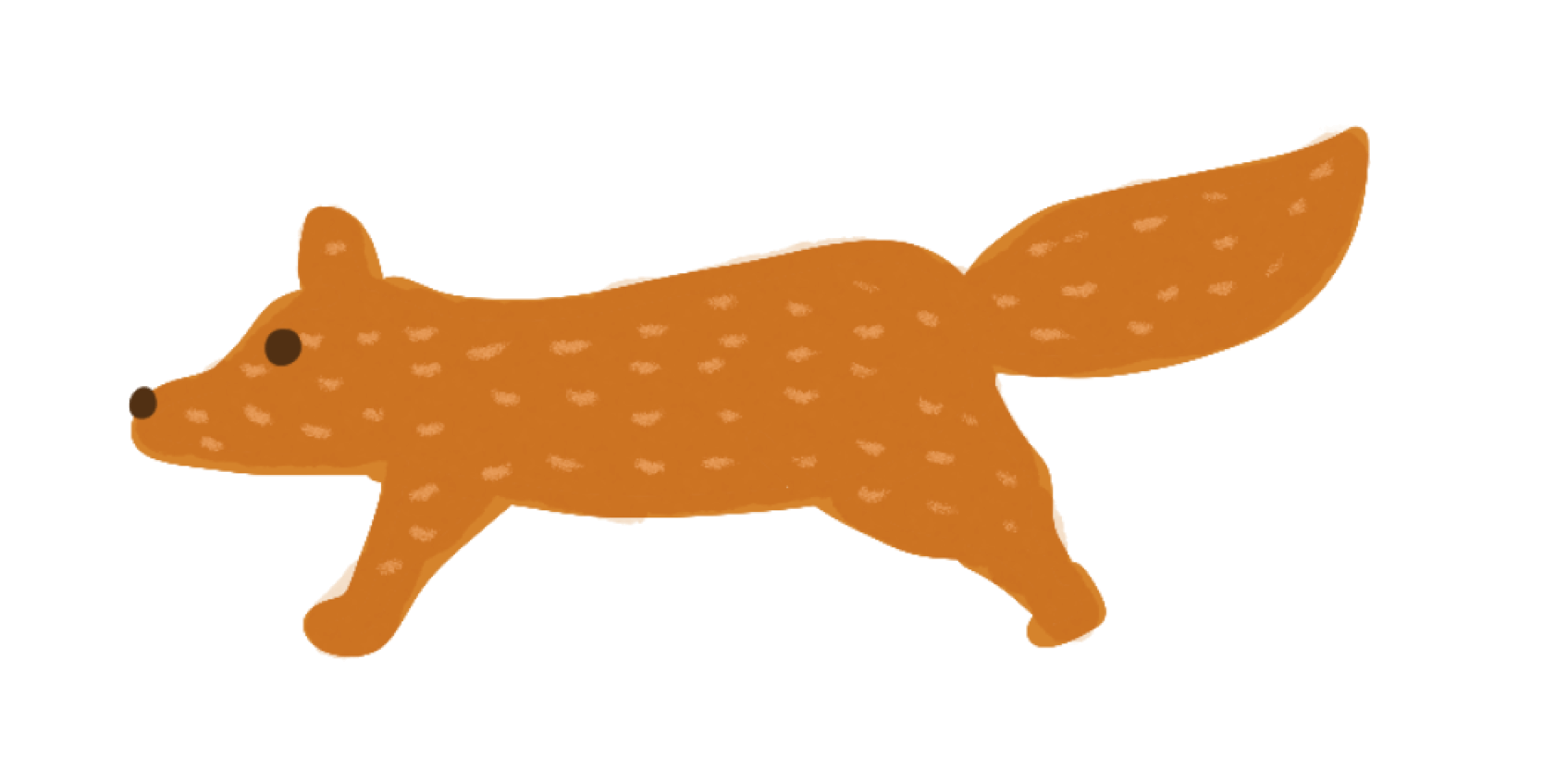
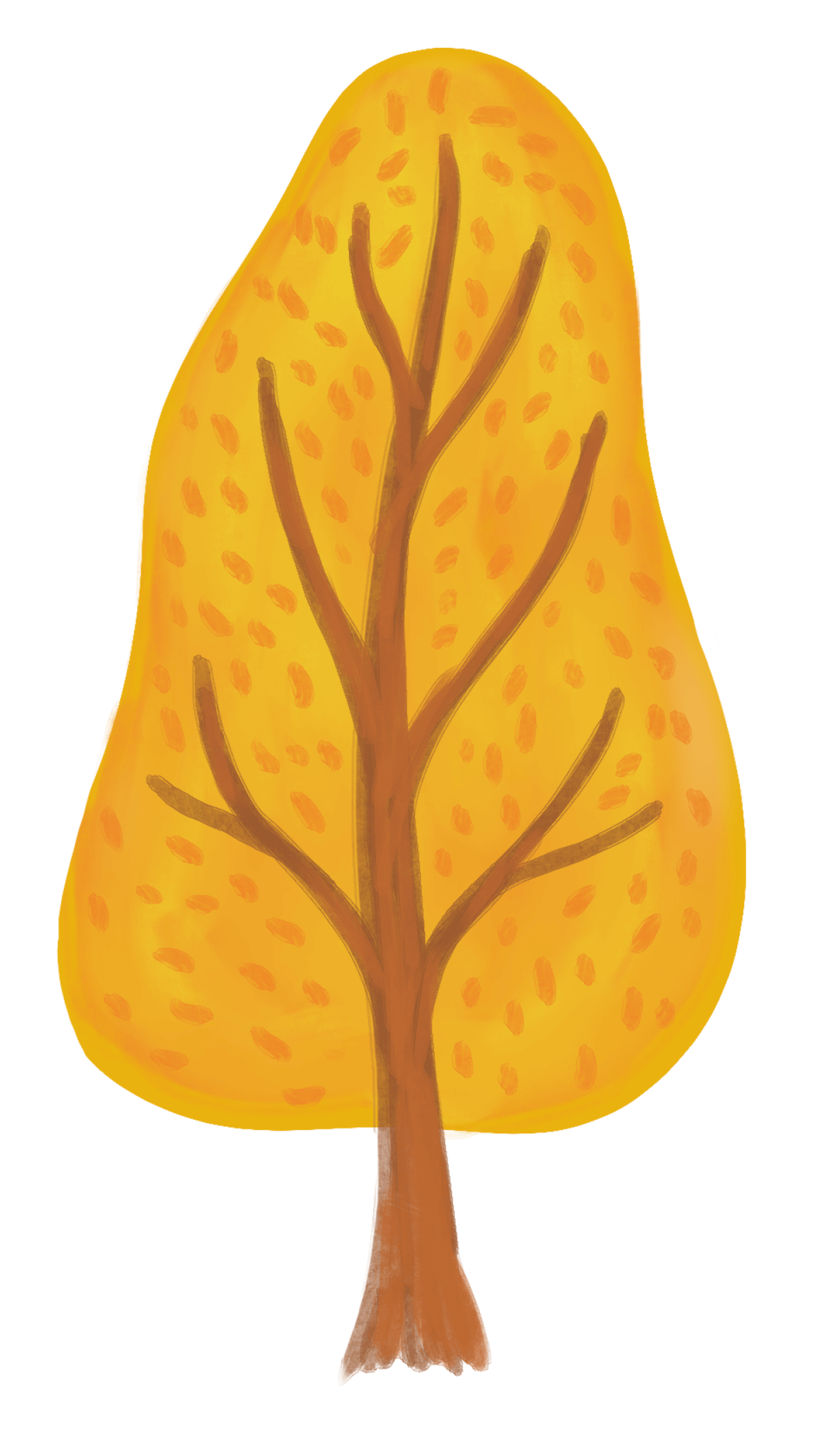


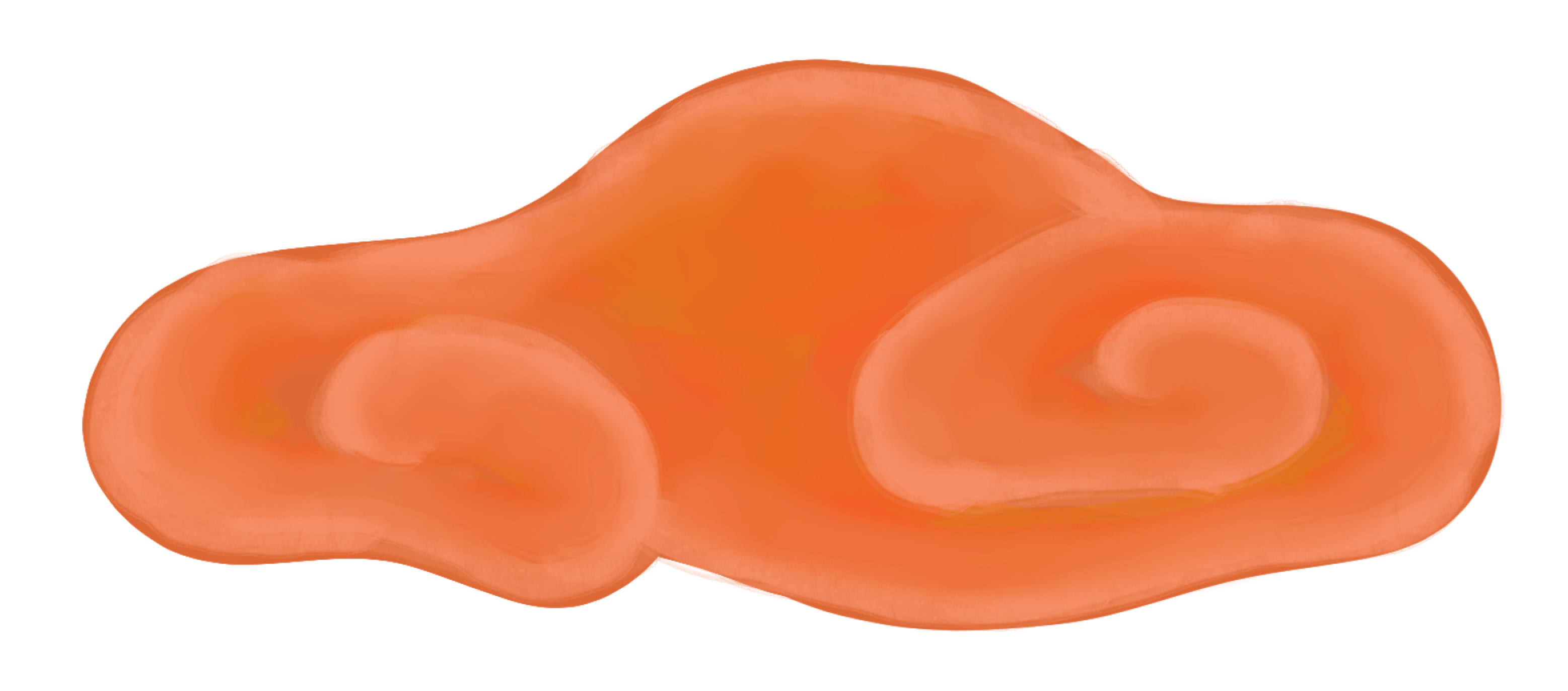

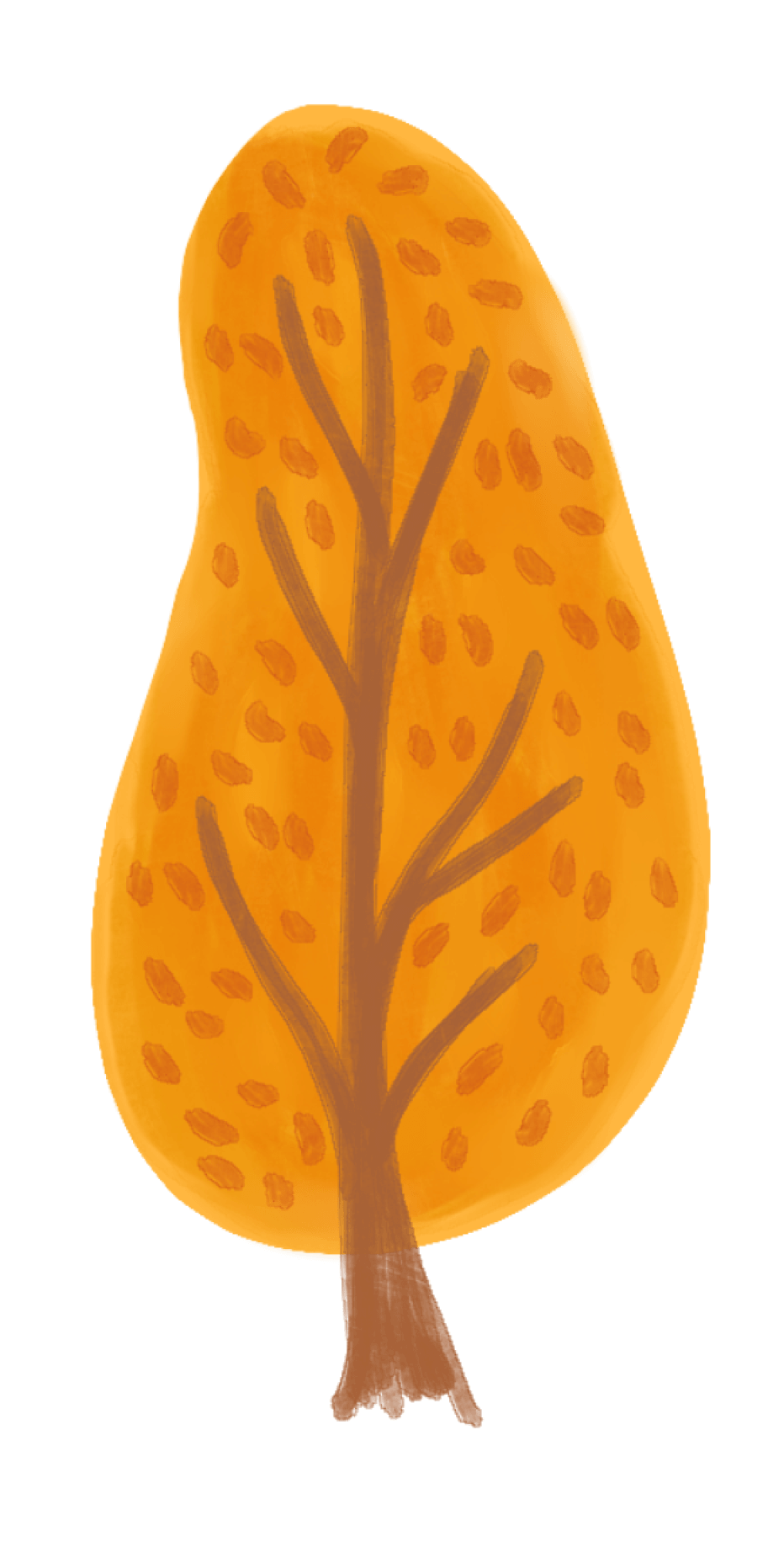
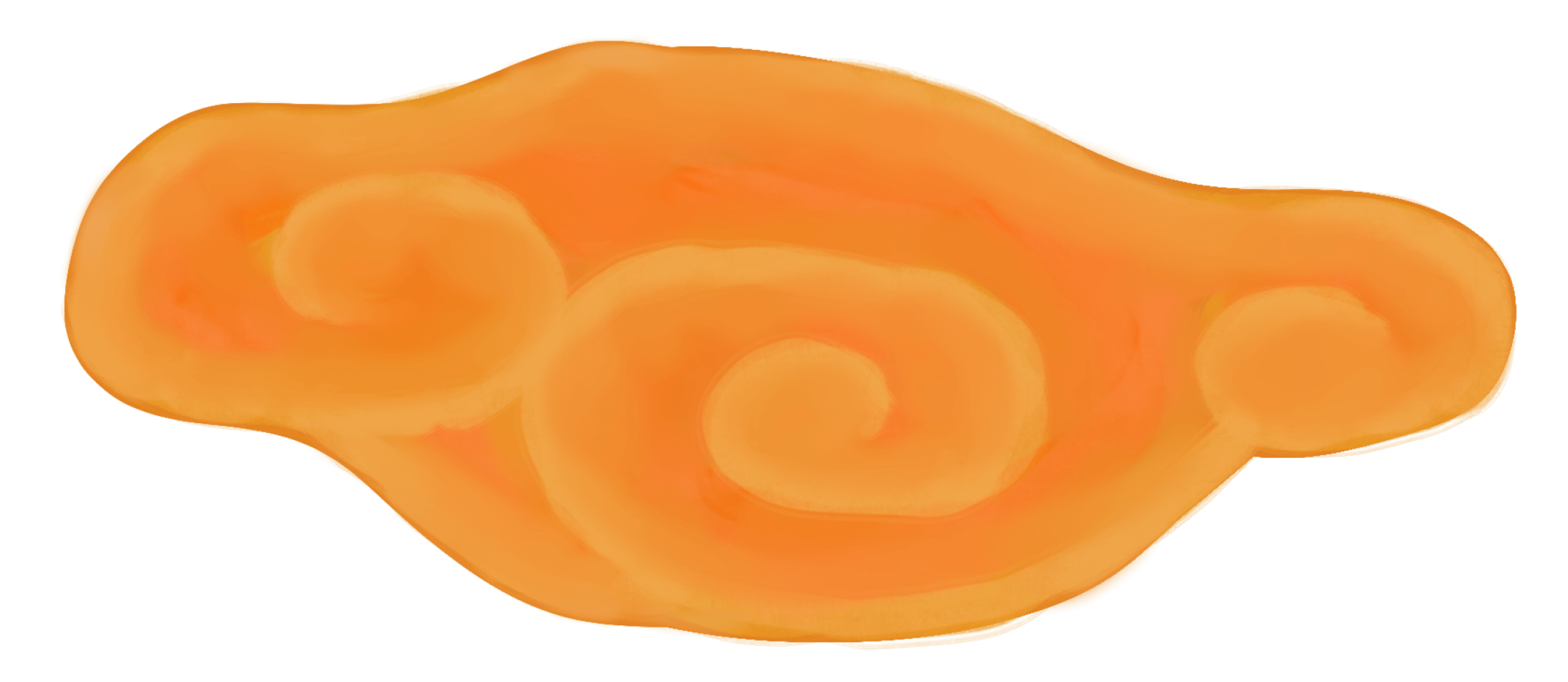
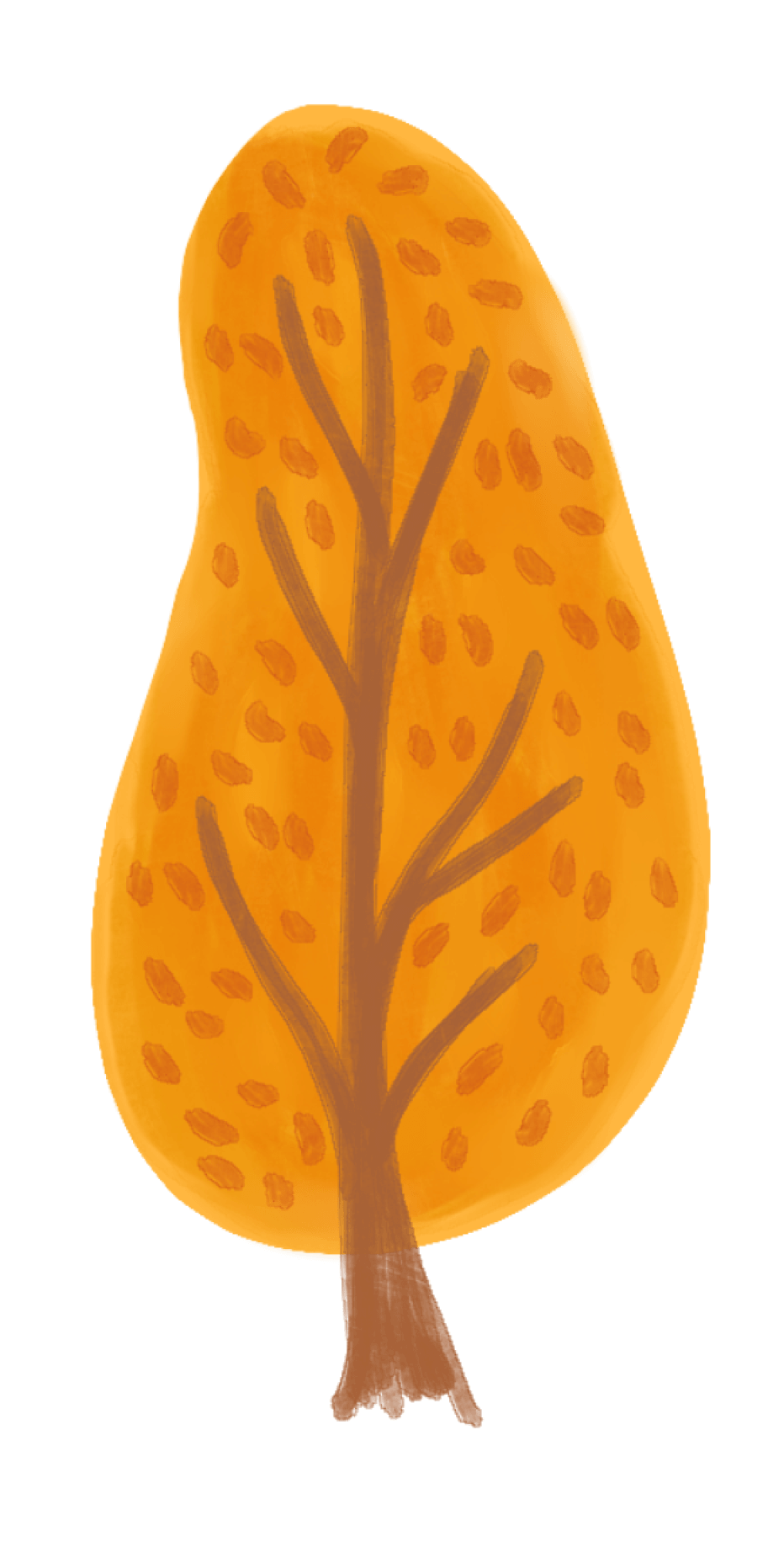

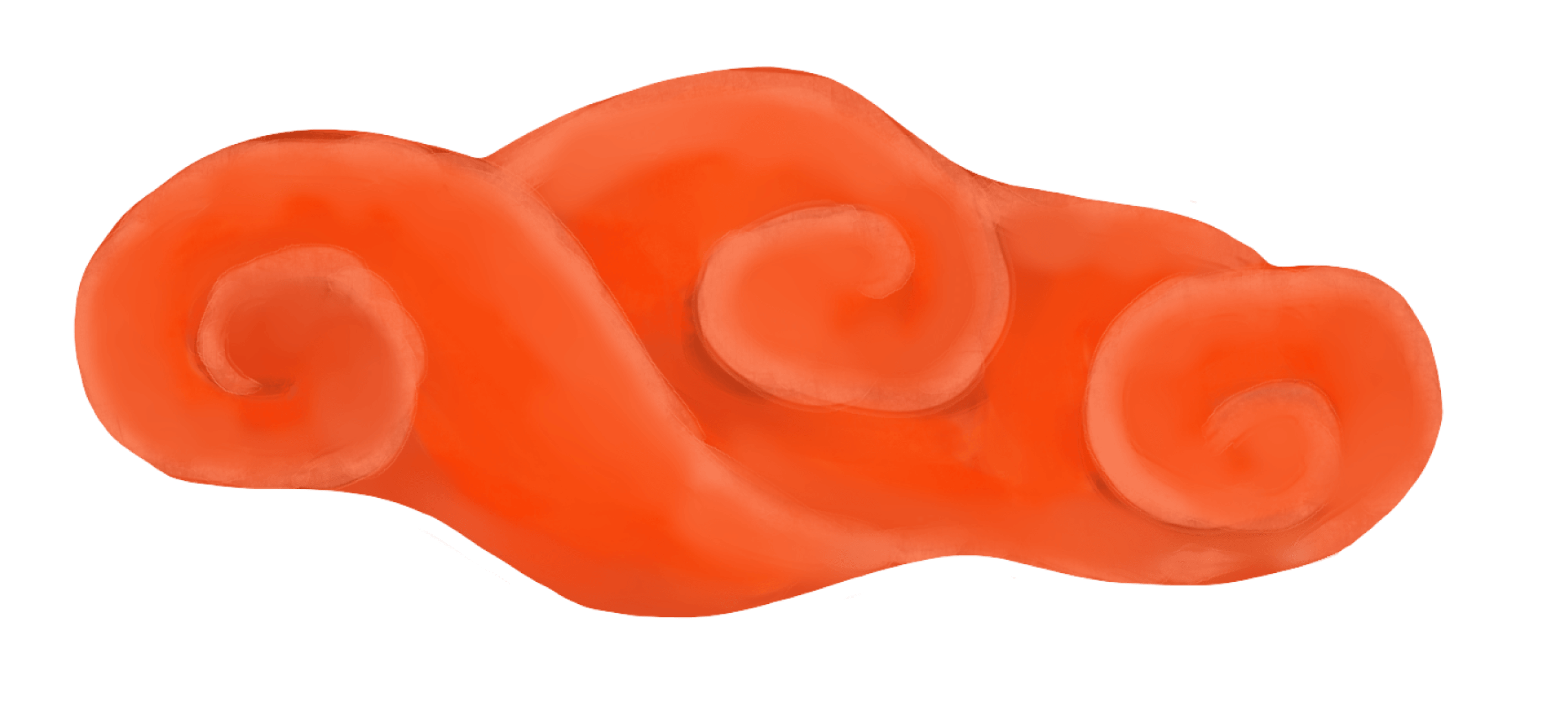
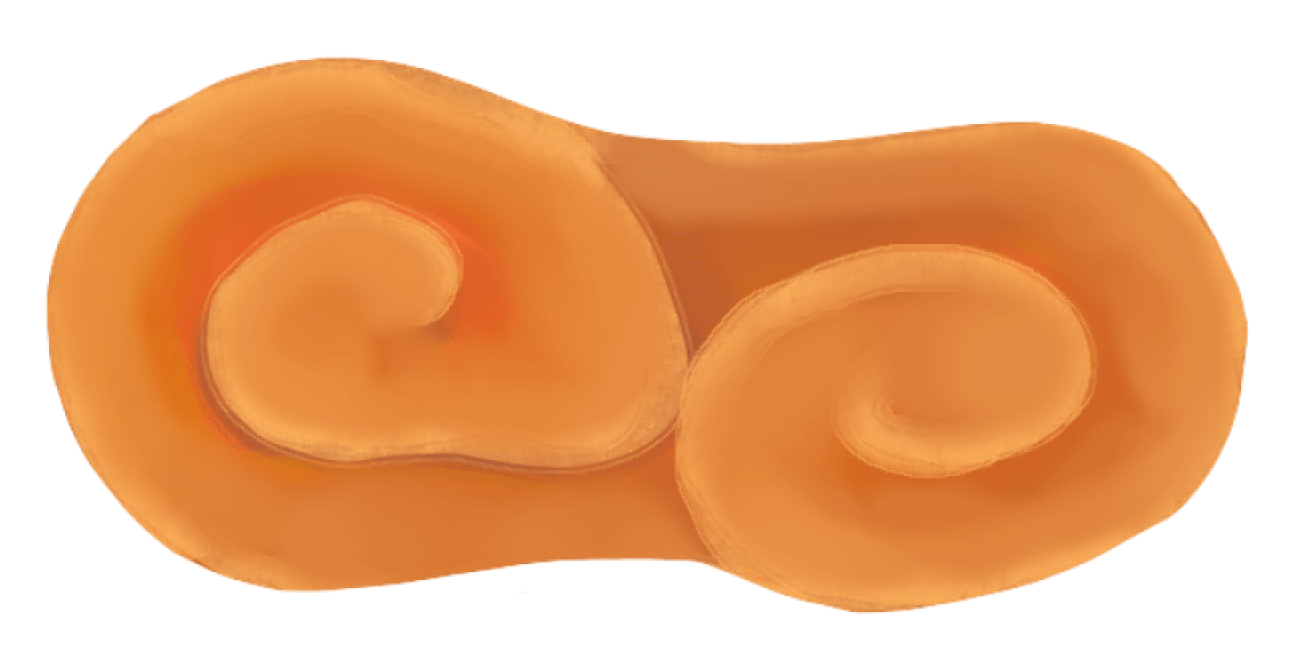
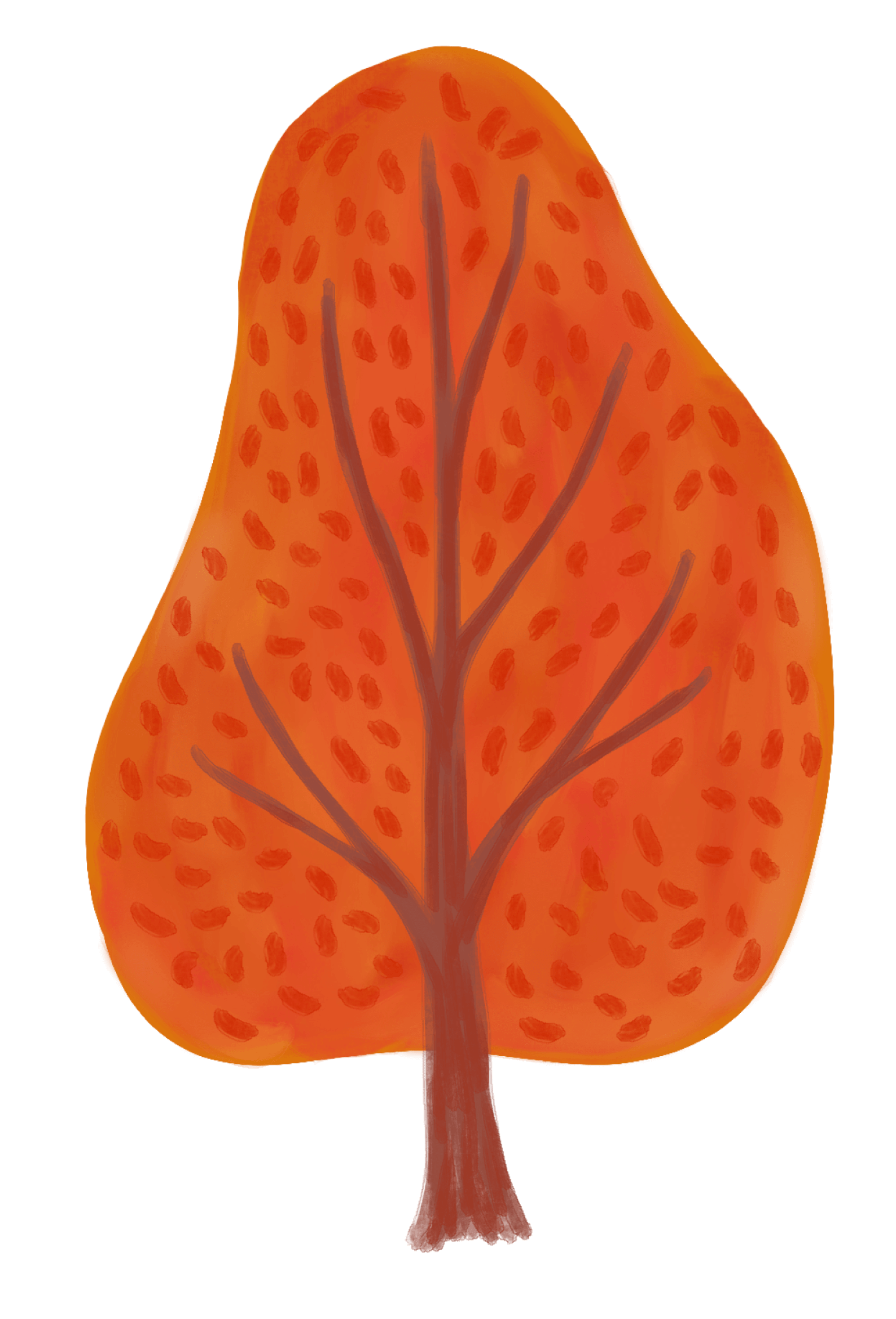

(やもとはちまんぐう)
紅葉退治のため戸隠を訪れた維茂が、妖術で姿をくらました紅葉の居場所を探るため矢を放ち占ったという場所。矢本神社とも呼ばれる。矢が落ちたとされる柵神社や、紅葉が拠点としていた荒倉山への眺望が開け、境内には維茂が弓を引く際に足を掛けたと伝わる「ふんばり石」が残る。

(しがらみじんじゃ)
維茂の放った矢が飛んでいった先に建つと伝わり、矢先神社とも呼ばれる。境内は鬱蒼とした木々に囲まれ、長い石段を上ると立派な彫刻が施された社殿が現れる。境内には「余吾将軍平維茂紅葉狩遺蹟之碑」が建ち、紅葉伝説の存在を今に伝えている。内田康夫の小説「戸隠伝説殺人事件」の第2の事件が起きていた場所。

(しがらみばし)
土合(どあい)集落の裾花川に架かる橋。維茂が放った矢を追う最中、難所として立ちはだかったという場所にある。当時、深い谷川には橋がなかったものの、倒木が柵(しがらみ)のように横たわり運よく川を渡ることができたと伝わる。この故事にちなみ「柵」という地名がついたとか。

(がんくつかんのんどう)
田頭(たがしら)集落の裏山に位置する、崖面の岩窟を利用した独特な懸造り(かけづくり)の堂。急斜面に巧みに組まれた架構により、断崖においても均衡を保っている。2018年、長野市の有形文化財に指定された。堂前には幹まわり8.6m、高さ45mの大杉が立ち、紅葉退治の戦いを前に維茂が必勝を願って手植えしたものと伝わる。入り口の妙見神社(みょうけんじんじゃ)から続く道沿いにはたくさんの石仏が並んでおり、信仰が盛んであった様子がみられる。

(あらくらきゃんぷじょう)
荒倉山の麓、標高約1,000mに広がる自然豊かなキャンプ場。伝説の中では「毒の平(ぶすのだいら)」というう戦いの中心地として登場。内田康夫の小説「戸隠伝説殺人事件」のはじめの事件が起きていた場所。バンガローや炊事場、五右衛門風呂などの設備が整う。鬼女紅葉の史跡巡りや荒倉山トレッキングの拠点として最適。場内の一角には能舞台があり、例年秋には鬼女もみじ祭りが開催される。
利用の際はご予約下さい
キャンプ場:商工会戸隠支所(026-254-2541)
能楽堂:北部産業振興事務所(026-254-2324)

(あらくらやま)
岩屋までの道中、紅葉の生活を思わせるスポットが点在。
舞台岩や紅葉の化粧水などこの伝説にちなんだ場所がある。

(きじょもみじのいわや)
戸隠と鬼無里にまたがる荒倉山の中腹に位置する岩窟。紅葉が戸隠・鬼無里の地へ流されたときの、住処として伝わる。切り立った崖に並ぶふたつの岩穴のうち、小さく深い方が根城だったとされる。荒倉キャンプ場入口から徒歩約1時間。

(おにのつか)
鬼女紅葉の墓とされる大きな高さ165cmの石造五輪塔のある場所。維茂との戦いで討たれた紅葉の首が埋葬されているとの伝承が残る。五輪塔は平安時代末から供養塔や墓として使われた。数十墓並ぶ小型の五輪塔は手下たちの墓とされる。柵神社から徒歩約5分の小高い丘に位置する。

(だいしょうじ)
紅葉の菩提寺として知られる曹洞宗の寺院。水田に囲まれたのどかな景色のなかに佇む。“紅葉と維茂を一緒にまつる位牌”と、謡曲の詞に合わせて“紅葉退治の様子を描いた画幅”が寺宝として伝わり、境内には紅葉と維茂の供養塔が建つ。表参道入口には「鎮守の大杉」と呼ばれる巨木がそびえる。

(とがくしちじつかせきはくぶつかん)
戸隠のことを語るなら必ず訪れたい博物館。紅葉伝説の中心地である柵エリアにあり、廃校を利用して作られた建物は当時の面影も残している。鬼女紅葉伝説はもちろん、博物学や地質学など科学の視点から戸隠について学べる。

(すずりいし)
紅葉の家来だったおまんは、維茂との戦いに敗れ逃げ込んだ先で、大きな石のくぼみに溜まった水に映る自らの姿を見て改心を誓ったという。出家後はこの石の水で墨をすり、習字の稽古に励んだとか。現在も硯石(すずりいし)の名で親しまれ、中社から鏡池への古道沿いに残る。北アルプスや荒倉山などの展望スポットでもある。

(いしがみさん)
中社エリアに建つ紅葉の家来“おまん”を祀る社。その健脚さにちなみ、足腰の守り神として今も信仰を集めている。おまんは維茂との戦いに敗れた後、この地で出家し尼として懺悔の日々を送ったが、最期は自ら命を絶ったという。その死を悼んで建てられたと伝わり「足神(あしがみ)さん」の愛称で親しまれている。